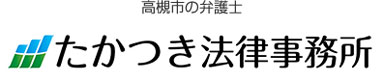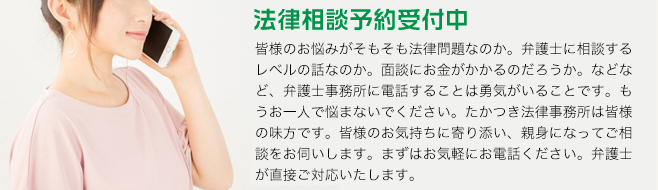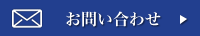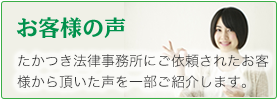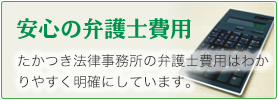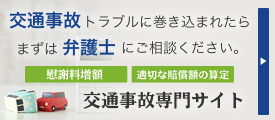相続のルール
日本では、民法が相続人の範囲や相続人の優先順位、相続分の範囲について規定しています。これを法定相続人、法定相続分と言います。
①配偶者
被相続人(故人)に配偶者(妻・夫)がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
②子供
被相続人の子供は、被相続人の配偶者とともに相続人になります。養子も同じです。
まだ産まれていない胎児も第1順位の相続人になりますが、死産の場合は相続人になりません。
子供がすでに死亡している場合は、孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
③親
子供や孫がいない場合は、親(父母)が相続人になります。
つまり、被相続人に子供がいなければ、配偶者と被相続人の親が相続人になります。配偶者が死亡していれば親だけが相続人になり、親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
④兄弟姉妹
被相続人に子供がおらず父母が死亡している場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
夫婦の間に子供がいない相続の場合
- 被相続人の配偶者は常に相続人になります。しかし夫婦に子供がいない場合は注意が必要です。
- 被相続人の親が存命のときは、配偶者と被相続人の親が共同相続人になります。
被相続人の親がいないときは、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が、共同相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子どもが相続人になります(代襲相続)。
今回のケースでは、夫が亡くなった夫婦に子供がおらず、配偶者である妻がいます。そこで、配偶者である妻は、第1順位の相続人として、夫の財産を相続します。
しかし、妻の法定相続分は、夫の家族構成によって変わってきます。
配偶者(妻)と夫の親が相続する場合
夫の親が存命の場合、夫の親も配偶者とともに共同相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、夫の親が3分の1となります。
配偶者(妻)と夫の兄弟姉妹が相続する場合
夫の親がおらず兄弟姉妹がいる場合、夫の兄弟姉妹も配偶者と共に共同相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
子供がいない夫婦で、配偶者にすべての財産を残したいと希望する場合は、最も有効な方法として遺言書を残すことが考えられます。